光触媒の最初の研究は?
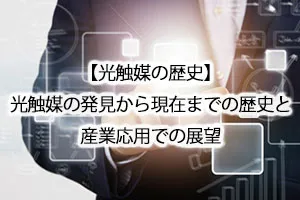
光触媒の発見と研究は、1911年に遡ります。ドイツの化学者アレクサンダー・アイブナーが、酸化亜鉛に光を当てると、濃青色の色素プロイセン・ブルーが漂白される現象についての研究において、光触媒の概念を用いたのが、始まりとされています。
それからしばらくは光触媒の研究は停滞していたようですが、光触媒の実用化は1960年代の日本の研究がきっかけとなりました。
1967年、東京大学の本多博士と藤島博士は、半導体電極として酸化チタン(ルチル型)、金属電極としてプラチナを用い、酸化チタン極に紫外光照射すると、酸化チタン極から酸素が、プラチナ極から水素が発生することを発見しました。
このように、酸化チタンに光を照射することによって、水が酸素と水素に分解される現象は、酸化チタン表面で光触媒反応が発生したわけです。この反応は後に『ホンダ・フジシマ効果』と呼ばれるようになりました。
この発見は、1972年に国際的な学術雑誌であるNatureに論文が掲載されました。
1970年代は第一次石油危機の時期にあたり、世界的に新エネルギーが求められたたこともあり、「太陽光で水から水素を無尽蔵に取り出す方法だ」ということで、国内外の研究者の注目を集めるようになりました。
酸化チタンを使った水素プラントの実用化に向けて、実際に太陽光下で一日間水素回収実験を行った結果、酸化チタン1m2あたりの水素発生量はわずか7リットルだったようです。それは照射された太陽光エネルギーのうちのわずか0.3%に過ぎなかったようです。太陽光だけで水素が発生することは、画期的なことですが、単結晶シリコンを使ったソーラーパネルの発電効率が15%以上あったことを考えると、変換効率が悪すぎです。
そのため、光触媒による水素製造の実用化へ向けた研究は、効率の悪さという課題を残していったんストップしました。
酸化チタンの除菌や消臭への応用研究
1980年代の後半になると、東大は方針を変更して光触媒の研究が再開されました。
そのときの研究テーマは水素の発生ではなく、酸化チタンの強い酸化力を活かして、微量な汚染物質の分解等に適用することが主な目標となったようです。当時、除菌や消臭に強く関心を持っていた東陶機器(現TOTO)基礎研究所と東京大学とによる共同研究が始まりました。
そのときに、酸化チタンをコーティングしたタイルを製造し、病院の手術室で効果を調べたところ、タイルを貼った床や壁ばかりではなく、空気中の細菌も減少していることが確認されました。空気中に浮遊している細菌がそのタイルに接触すると、光触媒反応で抗菌ができたわけです。
光触媒コーティング剤の開発
その頃、この光触媒が「有機物の分解に使えるのではないか」とのことで、日本中で光触媒の開発が進んでいきました。そして、その開発競争の中に佐賀県窯業技術センターの一ノ瀬博士が加わり、独自の製法で酸化チタンのアモルファス化に成功しました。
一ノ瀬博士は、1995年「チタニア膜形成用液体及びチタニア膜及びその製造方法 」で特許出願され、特許取得(特許番号2938376)されました。また、このアモルファス酸化チタンを元にして、酸化チタンのゾルである「アナターゼ分散液その製造方法 」で1997年特許出願され、特許取得(特許番号2875993)されました。
この一ノ瀬博士の発見によって、光触媒コーティング剤が比較的容易に製造できるようになり、光触媒が一般的に普及するきっかけとなりました。弊社もこの特許の恩恵を受け、光触媒コーティング剤の開発に乗り出しました。
光触媒による超親水性の発見
東陶機器基礎研究所と東大は、1995年に光触媒の「超親水性」の効果を発見し、論文に発表しました。超親水性とは、光が当たると光触媒の表面が水となじむ親水性の効果を発露するものです。
この効果を利用し、光触媒塗装面の防汚コーティングが研究されるようになり、セルフクリーニングができるようになりました。この効果を活用すると、高層ビルなどの窓ガラス清掃の手間を大幅に低減できます。このようにして、光触媒が産業応用される時代に入りました。
強力な光触媒反応を示す可視光応答型酸化チタンの発見
さらに光触媒の研究は進み、2002年には酸化チタンが200lxという弱い可視光でも、強い触媒反応を引き出す方法が発見されました。この方法を発見したのが弊社の研究スタッフでした。
もともと酸化チタンは紫外線にしか反応しませんが、重金属などの別の素材を酸化チタンに担持させることによって、可視光応答をさせられることが知られていました。しかし、室内の明るさでは抗菌や消臭には効果が弱いことが問題でした。
弊社は、佐賀県窯業技術センターの一ノ瀬博士が開発された「チタニア膜形成用液体及びチタニア膜及びその製造方法 」及び「アナターゼ分散液その製造方法 」を元にして、可視光の200lxでも活性があるような可視光活性光触媒が出来ないか開発を進めました。200lxと言えば、夜のリビングの明るさほどで、酸化チタンの室内利用を目指したものです。
2002年、「抗菌性コーティング液及びその製造方法並びにコーティング方法」で銅担持光触媒の製法の特許出願をし、特許取得(特許番号4203302)しました。この光触媒成分の発見により、金属などを担持させた酸化チタンの可視光活性化の研究が進むきっかけとなりました。
新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)は、光触媒の応用を検討しつつ、「屋内の可視光で使用出来る最高の可視光活性光触媒を開発する」とのことで、2007年度より東大を含む8大学やTOTOを含む11企業と共同で「循環社会構築型光触媒産業創成プロジェクト」を立ち上げました。
このプロジェクトでは、新しい光触媒の開発を進められつつ、銅ドープ酸化チタンのメカニズムの解明や効果の高さの実証がなされ、さらなる効果の高い可視光応答型光触媒の開発の可能性が拡がりました。
光触媒研究の展望
今後の研究としては、どのように展開するのか予想は難しいです。産業は、一つの発見によって大きくイノベーションすることもあるからです。
光触媒の活用によって野菜の熟成を抑えられることが20年以上前から知られていました。そのように、私達の身近な生活も光触媒の応用によって豊かなものになっていく可能性があります。
今では光触媒の研究は積極的に行われなくなったものの、新しい光触媒成分の研究も進んでおり、希土類を担持させた酸化チタンの開発や、それを使った水素の発生効率を高める方法も研究されており、弊社でも注目しています。
銅ドープ酸化チタンの産業応用では、身近なところでは脱臭機や化学物質の分解です。長期的には、宇宙ステーションや潜水艦などの密閉空間の居住性を高め、水質浄化の研究がなされる可能性も考えられます。
光触媒は、私達が普段見えないところで多く活躍していますが、今後はさらに利用範囲が増えることと思います。そのための課題は、光触媒の正しい選び方が認知されることかもしれません。光触媒が発見されてからまだ100年ちょっとです。光触媒の研究はこれからも進んでいきます。
この記事の著者/責任者

株式会社イリス 代表取締役
島田 幸一 (Shimada Koichi)
私はもともと、地元農業のソリューション提供を事業としていたが、野菜や果物の劣化を促進させるエチレンガスの分解を研究したことで、光触媒の可能性を感じ起業いたしました。運よく可視光でも効果のある酸化チタン光触媒を世界で初めて開発して脚光を浴び、さまざまな業種のお客様から注文をいただける企業にまで成長できました。現在弊社は、可視光応答型光触媒を使ったコーティング剤を始め、外壁やガラス、石材、自動車の車内にクリア塗装ができる光触媒コーティング剤や、酸化チタンから下地を守るプライマーの開発。その後も、さまざまな材質に光触媒を定着するための研究を続け、多くの企業で採用されています。
