
リフォーム工事で壁紙を新しいものに貼り直してもらった後に、接着剤の匂いで困る人もいるようです。
接着剤の匂いがするだけでしたら、換気をして、1~2週間ほど我慢したら良いわけですが、人によっては、「化学物質の匂いで体調が悪くなった」と言い張って、無理難題を言ってくる人もいます。
壁紙リフォームで、化学物質の匂いが気になる方がいらっしゃると、リフォーム業者としても困ってしまうことでしょう。
壁紙を貼り替えたところで、接着剤の匂いは壁にしみ込んでいるので、接着剤の匂いを完全に無くしたい場合には、壁紙だけでなく下地も交換する必要があります。
また、再度壁紙を貼ると、そこからまた化学物質の匂いが発生するため、それこそ漆喰や珪藻土を使うしかありません。
化学物質の匂いを気にされる方は、最初から壁紙の張り替えではなく、漆喰や珪藻土を使ってもらいたいところですが、壁紙リフォーム直後から、人生で初めて体調を悪くされる方もいらっしゃり、対応に困ることと思います。
この記事では、壁紙リフォームをして体調を悪くされてしまった方や、クレームを受けてしまったリフォーム業者さんに向けて、壁紙リフォーム後の化学物質対策について解説いたします。
化学物質の測定
壁紙リフォームで使用される接着剤は、通常であれば木工用ボンドのような臭いがします。その接着剤には、ホルムアルデヒド(HCHO)がほとんど含まれていないものを利用していると思います。
ところが、ホルムアルデヒドを使用していなくても、他の化学物質が使用されているので、リフォーム後の1週間以上、部屋の中は化学物質の匂いがすることがあります。人によって匂いに敏感な方もいらっしゃるので、「数か月は匂いがした」とおっしゃる方もいらっしゃいます。
施主様によっては、ホルムアルデヒドの匂いではなくても、化学物質の匂いがしたら、「ホルムアルデヒドだ」と決めつける方もいらっしゃるので、簡易的であってもホルムアルデヒド濃度の測定をなさった方が良いです。
とりあえず、クレームを受けられた業者様は、「ホルムアルデヒドの匂いがする」と言われることが多いので、ホルムアルデヒド濃度とTVOC濃度を測定できる機器をご利用なさってください。弊社にご相談いただけましたら、ハンディータイプの測定器で測定いたします。
ここで、TVOCとは、総揮発性有機化合物量「Total Volatile Organic Compounds」の略で、壁紙などから揮発してくる化学物質の総量です。ホルムアルデヒド濃度とTVOC濃度を測定しておいて、厚生労働省の指針値(厚生労働省ホームページ「室内空気中化学物質の室内濃度指針値について」を参照)と比較しておけば、本当に化学物質の影響かどうかを確認することができます。
この指針値を見ていると、13種類もの化学物質に指針値が決められているので、化学物質の匂いで体調不良があったとしても、ホルムアルデヒドだけが原因とは限りません。
化学物質の種類
厚生労働省が指針値を決めている化学物質の種類には、次のものがあります。
- ホルムアルデヒド
- アセトアルデヒド
- トルエン
- キシレン
- エチルベンゼン
- スチレン
- パラジクロロベンゼン
- テトラデカン
- クロルピリホス
- フェノブカルブ
- ダイアジノン
- フタル酸ジ―n―ブチル
- フタル酸ジ―2―エチルヘキシル
これら以外にも、シックハウスの原因物質は100種類とも200種類とも言われていますから、13種類の科学部資質の室内濃度が指針値以下であったとしても、体調に影響のある人もいます。化学物質対策が難しい理由は、ここにあります。
化学物質対策の基本
壁紙リフォームをした後に、化学物質の匂いがしてお困りの方に、ぜひともお試しいただきたい方法は、「換気」です。
とても原始的な方法ですが、換気は化学物質対策の基本です。
壁紙リフォームで化学物質が出てくる期間は、1~2週間ほどが多いと思います。その間は、ずっと換気を行って、外気を取り入れることで、室内の化学物質濃度を下げることができます。
ただし、真夏や真冬では、窓を開けて換気を行うことが困難なご家庭もあることでしょう。
そういったご家庭では、光触媒コーティング施工をおすすめします。
ホルムアルデヒド対策に効果的な光触媒
光触媒とは?
光触媒とは、光が当たることで、その表面に電子が飛び出し、その電子が空気中の酸素や水と反応して、OHラジカルと言われる活性酸素を発生させます。
OHラジカルは、強い酸化力を持つので、ホルムアルデヒドなどの化学物質と接触すると、その成分を二酸化炭素や水といった、匂いの無い成分に酸化分解する性質があります。
ただし、光触媒と言ってもいろいろな種類があり、一般的な光触媒では分解が難しい化学物質もあります。
そういったことで、光触媒コーティング施工は化学物質対策としては導入しやすいものですが、光触媒コーティング剤にどのような光触媒成分を利用しているのかによって、効果の高さに大きな差があります。
化学物質を分解できない光触媒の種類
光触媒といっても、いろいろな種類があります。光触媒コーティング剤として実用化されている主な光触媒の種類は、次のものがあります。
- 酸化チタン
- 銅ドープ酸化チタン
- 窒素ドープ酸化チタン
- 鉄ドープ酸化チタン
- 酸化タングステン
- タングステン担持酸化チタン
1つ目の酸化チタンは、紫外線が当たらないと効果が無い成分ですから、室内のホルムアルデヒドを分解したい場合には不向きです。なぜなら、室内には蛍光灯やLED照明といった、紫外線がほとんど出てない照明器具が使用されているからです。
2つ目の銅ドープ酸化チタンは、ホルムアルデヒド対策として、もっともおすすめの種類です。この効果については、後ほど詳しくご説明します。
窒素ドープ酸化チタン、鉄ドープ酸化チタン、ならびに酸化タングステンは、室内用として利用される光触媒ですが、銅ドープ酸化チタンと比べて1/10~1/20ほどの効果しかありませんから、おすすめしません。
タングステン担持酸化チタンは、ガラスの防汚コーティング用として利用されるものですから、ホルムアルデヒド対策には利用できません。
銅ドープ酸化チタンの効果
銅ドープ酸化チタンとは、ナノレベルの酸化チタン結晶の表面に酸化銅を結合させた光触媒です。
酸化チタン単体では、紫外線にしか反応しないため、室内のホルムアルデヒド対策には向いていませんが、銅ドープ酸化チタンは結合された補触媒であるナノレベルの酸化銅の効果によって、蛍光灯やLEDといった照明器具の光でも、効果があります。
しかも、酸化タングステンのように2,000lxとか1,000lxといった、手術室並みの明るい光がなくても、薄暗いリビングやトイレといった薄暗い部屋でも、ホルムアルデヒドを分解できます。
また、壁紙リフォームで揮発してくる化学物質は、ホルムアルデヒドだけとは限りません。トルエンやキシレンといったガスも発生する可能性があります。
トルエンやキシレンは芳香族と言われる、ベンゼン環を持つ化学物質です。ベンゼン環は、「光触媒では分解ができない」ということが業界でも常識なのですが、唯一、銅ドープ酸化チタンだけが分解ができます。
まとめると、銅ドープ酸化チタンは、薄暗い光でもホルムアルデヒドを分解し、他の光触媒では分解ができない化学物質をも分解する性質があります。この銅ドープ酸化チタンを、壁紙全体に塗布しておくと、ホルムアルデヒド対策ができます。
トルエンやキシレンの分解については、「いろいろな種類のVOCを除去できる銅ドープ酸化チタンの魅力」をご参照ください。
光触媒コーティング施工
光触媒コーティング施工とは、光触媒成分を添加したコーティング剤を塗布する施工方法です。光触媒成分を添加したコーティング剤のことを、光触媒コーティング剤といいます。
光触媒コーティング施工は、施工業者様も習得されて施工ができますが、クレームになっている場合は急ぎですから、弊社もしくは弊社の施工代理店にお任せください。
銅ドープ酸化チタンを使った光触媒コーティング剤
銅ドープ酸化チタンを使った光触媒コーティング剤は、弊社製品にはいろいろな種類がありますが、壁紙リフォーム後のホルムアルデヒド対策には、屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)を用います。
屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)の成分は、銅ドープ酸化チタンとアモルファス酸化チタン、水だけです。有機溶剤を利用していませんので、壁紙のホルムアルデヒド対策に向いています。
| 光触媒成分 | 銅ドープ酸化チタン |
|---|---|
| 接着成分(バインダー) | アモルファス酸化チタン |
| その他 | 水 |
銅ドープ酸化チタンは、ホルムアルデヒドだけでなく、細菌類や匂い成分、アレルゲンなども分解できるので、部屋のホルムアルデヒド対策だけでなく、抗菌、消臭、防カビ、アレルゲン対策などといった効果もあります。
光触媒コーティング剤を塗布するスプレー装置
光触媒コーティング剤の塗布には、専用のスプレー装置を用います。弊社では、ABAC(アバック)温風低圧塗装機を推奨しています。
次の写真は、ABAC温風低圧塗装機SG-91です。

青色の装置がブロワーです。電源をONにすると温風が噴き出し、ホースを通してスプレーガンに温風を供給します。
スプレーガンの塗料カップに、光触媒コーティング剤を充填し、壁紙に向かってスプレーします。
壁紙に光触媒コーティング剤を塗布する方法

上記のスプレー装置を用い、壁紙リフォームした箇所全体にスプレーします。
ホルムアルデヒドは、銅ドープ酸化チタンによって比較的簡単に分解できるので、ホルムアルデヒド対策では、屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)を通常の抗菌・消臭コーティング施工と同様に、2回塗布します。
1回目の塗布後に、液剤を乾燥させて、その後に2回目の塗布を行います。
乾燥には、夏であれば30分ほど、冬であれば暖房をかけて1時間ほど待ちます。液剤は塗布後に5分ほどで乾きますが、接着成分が固まるまで待ちます。
通常の塗布では、クリア塗装と言って、透明な塗装ができるので、塗布後に壁紙が変色することはございません。
光触媒コーティング後の効果
壁紙に屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)を塗布すると、壁紙から出てくるホルムアルデヒドが、壁紙の表面にある銅ドープ酸化チタンに触れて、その場で分解されます。
分解後は、水と二酸化炭素といった無害なガスになります。
ホルムアルデヒドが分解されないで部屋の中に出てしまっても、部屋の中を漂って壁に触れたら分解されます。

銅ドープ酸化チタンを使った光触媒コーティング施工をされた多くの方は、「部屋の空気が浄化されたようだ」とお感じになられます。ホルムアルデヒド対策では、施工後すぐにホルムアルデヒド濃度が下がっていることをご確認いただけます。
施工の流れ
施工の流れは次の通りです。
- 施工前のホルムアルデヒド濃度測定
- 部屋の片付けや家具の移動
- 塗布面の清掃
- 養生
- 屋内用プライマー(AS01)の塗布
- 乾燥
- 屋内用光触媒コーティング剤(BX01-AB1)の塗布
- 乾燥
- 施工後のホルムアルデヒド濃度測定
- 片付け・復旧
- 紫外線ランプの設置(場合によっては)
ホルムアルデヒド濃度測定は、ハンディータイプの簡易的な測定を行っています。本格的な測定をご希望の方は、外部の業者に委託することになるので、高い費用と時間がかかってしまうことをご了承ください。
養生とは、光触媒コーティング剤を塗布しない箇所にビニールシートや養生テープを貼って保護することです。養生する箇所としては、照明器具、家電製品、ガラス、観葉植物といったものです。
屋内用プライマー(AS01)とは、下地保護剤のことです。屋内用プライマー(AS01)を塗布する箇所は、部屋の中で直射日光が当たる箇所です。直射日光が当たる箇所は、銅ドープ酸化チタンが強く反応するため、その箇所が色あせする可能性があるので、それを防止するために、あらかじめ屋内用プライマー(AS01)を塗布します。

紫外線ランプの設置は、ホルムアルデヒド濃度が高い場合や、ホルムアルデヒド以外の化学物質を対策した場合に使用します。
紫外線ランプを設置しておけば、銅ドープ酸化チタンが強く活性化するので、化学物質の分解が促進されます。
化学物質対策をお急ぎの方や、部屋の中が薄暗い場合は、紫外線ランプを設置します。
ホルムアルデヒド対策のご依頼
一般のご家庭で、「ホルムアルデヒド対策を相談したい」もしくは「依頼したい」という方は、弊社までご連絡ください。ご連絡方法は、お電話(0955-41-0011)もしくはお問い合わせフォームにてお願いします。
お問い合わせフォームでご連絡を頂きましたら、こちらかお電話を差し上げます。お電話にて、ホルムアルデヒド対策のご依頼経緯をお教えください。
施工は、弊社もしくは弊社の光触媒製品を扱う施工代理店にて行います。弊社での施工は、主に福岡県、佐賀県、長崎県です。それ以外の場所は、施工代理店にて対応いたします。
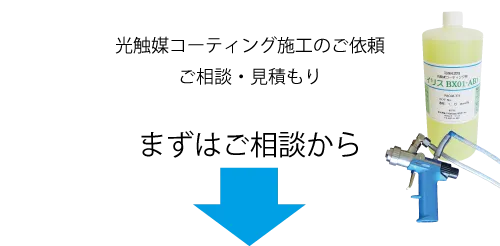
この記事の著者/責任者

株式会社イリス 代表取締役
島田 幸一 (Shimada Koichi)
私はもともと、地元農業のソリューション提供を事業としていたが、野菜や果物の劣化を促進させるエチレンガスの分解を研究したことで、光触媒の可能性を感じ起業いたしました。運よく可視光でも効果のある酸化チタン光触媒を世界で初めて開発して脚光を浴び、さまざまな業種のお客様から注文をいただける企業にまで成長できました。現在弊社は、可視光応答型光触媒を使ったコーティング剤を始め、外壁やガラス、石材、自動車の車内にクリア塗装ができる光触媒コーティング剤や、酸化チタンから下地を守るプライマーの開発。その後も、さまざまな材質に光触媒を定着するための研究を続け、多くの企業で採用されています。
